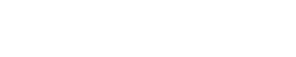 |
|
|
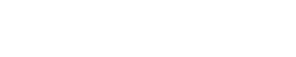 |
このモニュメントは、二上山から採れるサヌカイトと呼ばれる石をモチーフにして作られたもの。大昔の人とサヌカイト、そしてこの場所(翠鳥園遺跡)は、切っても切れない縁があるのだ。かつて翠鳥園遺跡の発掘調査が行なわれたとき、サヌカイトの石器類が約20000点も見つかった。これは今から2万年前、この場所が旧石器人が石器を作った
場所であったことを示している。モニュメントの中に入ってみると、金属に似た不思議な音色が流れてくる。これはサヌカイトを叩いたときに出る音を使ったものだ。公園内では、その他、旧石器人の生活を解説したビデオ上映や、石器類の模型の展示なども行っており、訪れる人たちは、気軽に旧石器人の文化に触れることができる。
|
白鳥(しらとり)神社 のだんじり祭りに使用
もとは、軽里(かるさと)地区の西方の伊岐谷(いきだに)に祀られ「伊岐宮(いきのみや)」といわれていた。その後、南北朝や戦国の戦火にかかって次第に衰微し、峯ケ塚古墳(みねがづかこふん)に小祠として祀られていたが、1596年慶長の大地震で倒壊し、そのまま放置されていた。
江戸時代の寛永末期に現在地に移され、日本武尊(やまとたけるのみこと)と素戔鳴命(すさのおのみこと)を祭神とする古市の氏神となった。10月8. 9の両日に行われる秋祭りでは、古市各町の地車(だんじり)が宮入りする勇壮な姿が見られる 。
|
羽曳野丘陵から東側に延びる低い舌状の尾根に築造された前方後円墳で、墳丘長は190m。宮内庁により「日本武尊白鳥陵(やまとたけるのみことはくちょうぼ)」に治定され、墳丘は精美な姿で残っている。
前方部を西に向け、墳丘は三段築成で、くびれ部両側に造出しを備えている。周囲には幅約35mの濠と上面幅21mの堤をめぐらせていることが羽曳野市教育委員会の発掘調査によって確認された。墳形は前方部幅が後円部径の約1.5倍で、高さも前方部が3m高い特徴がある。
1981年に宮内庁によって実施された墳丘裾崩壊箇所の発掘調査では、後円部の円筒埴輪列が確認されたほか、朝顔形埴輪や家、蓋などの形象埴輪が出土している。円筒埴輪は市野山古墳(允恭陵)と同様な特徴が見受けられ、築造年代は5世紀後葉頃と推定される。
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |