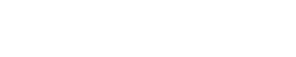 |
|
|
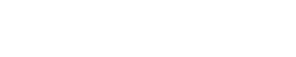 |
古市古墳群のほぼ中央に位置し、墳丘長225mを測り、古市古墳群内で5番目の規模を誇る大型前方後円墳。現在、墳丘は「応神天皇陵」の「陪冢」として宮内庁に管理されている。
前方部を西に向け、墳丘は三段築成で、くびれ部両側に方壇状の造出しを備えている。周囲には幅約15mの濠と幅約37mの堤をめぐらせ、市野山古墳(允恭陵)や茨木市の太田茶臼山古墳(継体陵)ときわめてよく似た規模と平面プラン。
後円部頂には格子目を刻んだ竜山石製の石棺の蓋石が露出していたことが報告され、津堂城山古墳や奈良県御所市の室大墓古墳と同様の石棺が用いられたと推測される。また、後円部頂から出土したと伝えられる多量の滑石製勾玉や家・盾・靱・短甲等の形象埴輪が宮内庁に保管されている。
前方部南側の外堤で実施された発掘調査では堤内側の斜面に葺石が施されていることが確認され、転落した円筒埴輪や盾・人物等の形象埴輪が出土している。
出土した埴輪、石製品や石棺の特徴から築造年代は、5世紀前半代と推定される。
|
墓山古墳の陪塚のひとつ
一辺約67メートルの方墳。墳丘は二段築成。葺石が施され、幅約15メートルの濠をめぐらせている。古市古墳群のほぼ中央に位置し、墓山古墳の西に築かれた陪塚である。別名「前墓山古墳」とも呼ばれている。この墓山古墳の周囲には4基の方墳が配置されているが、こうした巨大古墳の周辺に随伴する小型古墳を一般に陪塚と呼んでいる。
発掘調査では円筒埴輪・盾などの形象埴輪が出土しており、浄元寺山古墳自体は、5世紀中ごろに築かれたものと推定されている。
|
径65メートルの円墳で、墳丘の南西部分には、造出しと呼ばれる、幅25メートル、長さ17メートルの方形の突出をもっている。墳丘のまわりには濠がめぐっている。濠の調査では、円筒埴輪や家・衣蓋・盾・靫・馬・人物形などの形象埴輪が見つかった。この古墳は5世紀中葉に造られたもの。
さて、青山古墳の南側で青山住宅を造成する際に大阪府教育委員会が昭和53年(1987)に発掘調査を実施している。調査では、前方後円墳1基、方墳4基が見つかっている。新たに見つかった5基の古墳は、青山古墳を1号墳として、青山2〜6号墳と名付けられた。これらをまとめて青山古墳群と呼んでいる。これらは5世紀中葉から末葉にかけて造られたもの。
ところで、青山1〜6号墳は東と西の大きく二つのまとまりに分けられる。そして、東のまとまりは1号墳→4号墳→2号墳の順、西のまとまりは、6号墳→5号墳→3号墳の順に造られたことが分かっている。このことは、5世紀中葉から末葉にかけて二つの集団の長が3世代にわたり、一定の共通の空間の中で古墳を造り続けた結果であると考えられる。そして、この二つの集団はお互いに親密な関係にあったことも想定される。
藤井寺市教育委員会が平成11年(1999)に青山古墳(1号墳)の東側で実施した調査でも新たに円墳が見つかり、青山7号墳と名付けられた。
なお、青山古墳群の南側の羽曳野市域では軽里古墳群が見つかっているが、その立地からみて、この二つの古墳群は相互に関連づけて考える必要がある。
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |