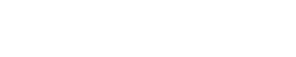 |
|
|
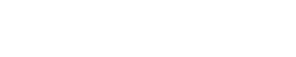 |
伝統ある王地山焼の復興を図り、市民の健康と生きがいづくりに資するため、篠山市王地山陶器所華工房(陶器所」)が設置された。
|
妙長山本経寺は日蓮宗に所属し、総本山は身延山久遠寺で、本尊は宗祖日蓮聖人奠定の大曼荼羅御木像である。慶長6年(1601)高崎の城主松平安房守信吉が実母(徳川家康姉)菩提のため、家臣都築和泉に奉行を命じ、茨城県土浦の地に建立した寺で、開山持経院日泉上人を派遣した東京都大田区池上、大本山本門寺の末流となる。
元和5年(1619)松平安房守信吉、丹波篠山城主としての転封の折り、本堂を解体し船に乗せ瀬戸内海に入り、加古川口より曳き船に乗せ替え久下に着き、そこから牛車にて陸送し、河原町の現在地に敷地を賜り移築建立された。山号寺号はそのままとし、京都大本山妙願寺の末寺となる。
|
旧街道の面影を残した町並みの河原町は、築城後まもなく町づくりがはじめられ、城下町篠山の商業の中心として大変栄えた。家並みは、妻入商家に代表され、5〜8mほどの狭い間口、しかし奥行きは大半が40m以上と深く、表構えの大戸、千本格子や荒格子、蔀(しとみ)、中二階の出格子、ムシコ窓、袖壁などが残り、往時の姿を今に伝える素晴らしい景観を織りなしている。
|
丹波古陶館は、丹波焼の創世記から江戸時代末期に至る七百年間に作られた代表的な品々を、年代・形・釉薬・装飾等に分類して展示している。なお、蔵品中312点は兵庫県指定文化財となっている。 また、篠山には文久元年(1861)に藩主が寄進した能楽殿が春日神社の境内に遺されており、現在も演能が催され、
全国で唯一の能楽資料館とともに、伝統芸能の一拠点となっている。更に、篠山城跡を中心とした市街地には篠山市立歴史美術館等の施設があり、これら諸施設の存在は篠山地方の文化の高さを示しています。なお、館蔵の「古丹波コレクション」は初代館長中西幸一と二代館長中西通が約80年に亘り蒐集してきたものである。
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |