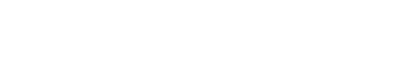 |
|
|
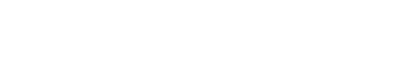 |
会員・ゲストの紀行アルバムです
|
ここまでは左右に商店の連なる参道の坂道や石段を登ってきたが、ここからはエスカレーター4本を繋いで「江ノ島サムエル・コッキング苑」なるところまで上る。江ノ島サムエル・コッキング苑は植物園でもあり、海沿いにに多いと云う、石蕗の花を将に実感した。
江ノ島神社は、辺津宮、中津宮、奥津宮に分かれ、宗像三女神を祭神とする。社伝では6世紀欽明天皇の頃の創建と伝える。鎌倉時代には将軍の参詣があり幕府の祈願所ともなった。江戸時代徳川家康が社領の寄進をし、広く信仰を集めたことから、江の島詣が流行した。裸形の弁天坐像は日本三弁天のひとつに数えられる。
|
裕次郎灯台方面を望む
裕次郎灯台遥か冬うらゝ 如水
「江ノ島サムエル・コッキング苑」内に平成15年に出来た「展望灯台」へ、エレベーターで昇る。海抜119.6mを誇るもので、晴天なら富士山も見えるとの由。
|
江ノ島の花嫁御料菊日和 如水
ウインドサーフィンが取り持つ仲だったのだろうか
|
再び江ノ電にて「長谷寺駅」へ。先ず、優先度の高い大仏へと足を向ける。流石、鎌倉の名所。駅からの歩道は左右とも押すな押すなの人の列だった。朝の円覚寺とは比べようもない。
|
大仏の慈悲なるお顔冬の空 いくら
正称は高徳院。国宝阿弥陀如来坐像(鎌倉大仏)を本尊とする浄土宗の寺。大仏は青銅製で、台座を含め高さ13.35メートル、顔の長さ2.35メートル、目の長さ1メートル、耳の長さ1.9メートル、重量約121トン。東国にも大仏を造ろうとした源頼朝の遺志を受け継ぎ、仕えていた稲多野局が計画したといわれる。暦仁元年(1238)に着工され、
6年後に完成した。しかし、最初の大仏は木造であったため台風によって崩れてしまい、その後建長4年(1252)から青銅の大仏が鋳造された。一辺1〜2メートルの鋳型を下から徐徐に接ぎ合わせて造られたが、原型作者も棟梁となっていた鋳物師も明らかになってはいない。このとき一緒に建立された大仏殿は、室町時代、大地震による津波で海に流された。
以来、ずっと露座のままである。津波で寺も流され、長く廃寺と化していたが、江戸時代の正徳2年(1712)、増上寺の祐天上人が豪商野島新左衛門の協力を得、寺と大仏を復興し、現在に至る。大仏は体内が空洞になっており、中に入ると頼朝の守り仏や祐天上人像を見学することができる。境内には女流歌人与謝野晶子が詠んだ
「鎌倉や御仏(みほとけ)なれど釈迦牟尼(しゃかむに)は美男におわす夏木立かな」の歌碑が立つ。
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |