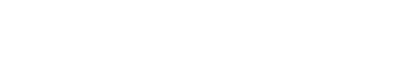 |
|
|
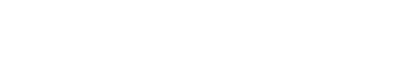 |
会員・ゲストの紀行アルバムです
|
朝飯前に氷見のホテルの窓から、昨夜の雪が積もっている。当地でのこの時期の雪は珍しいおのこと。(永井さん撮影)
|
朝飯後、ホテルの庭にて(永井さん撮影)
|
延享2年(1745年)坂下町極楽寺の第15世住持等誉上人の発願により、坂下町の坂道を上りつめたところ、定塚町に建立された木造金色の大仏が高岡大仏の起こり。以来70余年、高岡の一名物となって町民から親しまれていましたが、文政4年(1821年)の大火で惜しくも類焼した。しかし、時の住職第26世譲誉上人の熱心な再興の訴えで、
地元の坂下町民、定塚町民が立ち上がり、20年後の天保12(1841年)遂に復興した。ところがそれから60年後、明治33年(1900年)の大火で再び焼失した。現在のものは再び焼けることのない鋳銅仏にしたいとの願いから、広く各地に勧進して30年の努力の末昭和8年に完成した。原型、鋳造とも高岡工人の手によるもので、
「銅器の町 高岡」の象徴であるとともに、奈良、鎌倉の大仏とともに日本3大仏の一つに数えられている。(高崎さん撮影)
|
加賀藩二代藩主前田利長公の菩提寺。加賀藩百二十万石の財力を如実に示す江戸初期・禅宗に典型的な建物群である。仏殿、法堂、山門が国宝に、総門、禅堂、高廊下、回廊、大茶堂が重要文化財に指定されている。瑞龍寺の伽藍配置は、典型的な禅宗建築の様式で、総門、山門、仏殿、法堂を一直線に配し、回廊は山門から法堂まで左右対称に配置されている。右の回廊に大庫裏、大茶堂、左の回廊に禅堂が置かれ、七堂伽藍となっている。(高崎さん撮影)
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |