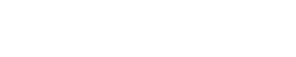 |
|
|
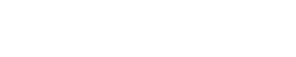 |
加集山万福寺:幸せの釣り方を授けるみ寺
恵美酒神(律儀の神)
ご詠歌:釣り上げし鯛を宝とだきかかえ笑う恵美酒は福徳の神
えびすさまの左手の鯛は「めでたい」のたい、一般には「芽出る」の意味がある。若芽がやがて大樹になるように、何か良くなる「兆」を芽出たいとなった。今、色々と叶えて欲しい悩み。その「何とかして解決を」と努力する姿こそが幸福への芽であり、めでたいのである。右手の釣り糸一筋は礼儀を重んじ、迷いなく人間らしく一筋に生きぬけとの示唆である。
縁起:宝亀年間(770〜)淳仁天皇の御陵と、御母当麻夫人の墓守を勤める僧侶の宿坊として草創されたが、時代の変遷と共に、いつしか廃退していった。応永年間(1394〜)になり、当地に館を構えた加集氏により堂宇を再興し、御陵の安穏と民衆の安泰を祈念する寺院として今日に継承されてきた。本尊の大日如来像二体を合祀する須弥檀は、非常に貴重な様式である。
|
賀集山護国寺:家庭円満・和合を授けるみ寺
布袋尊(和合の神)
ご詠歌:限りなく宝の布袋みてはげめ、笑う門には福来るなり
「この世の中は五濁悪世」と嘆いてばかりおれはせぬ。清濁も合わせ呑みこむハラをもち、背負った袋は宝物、だけど自分のものではない。困ったひとへの贈り物。年に一度のサンタクロースどころではない。左右の大きな耳たぶは、他人の話を聞き分けて、言ってはならぬことは耳たぶへ、ためて大きくなった。布袋尊は仲よく暮らせる人間の理想の姿を現したものである。
縁起:行教上人開創の由緒ある古刹で、本尊の大日如来坐像は、慈願に満ちたお姿で胎蔵界を表し。千年の歴史を偲ばせる。行教上人は、大和大安寺の僧侶で三輪宗及真言宗を学び、後に伝灯大法師に任じ、貞観元年(869)豊前宇佐八幡神宮に参詣し二年余りをここに過ごした。行教上人有縁の史跡と言えよう。
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |