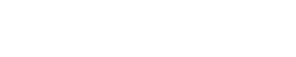 |
|
|
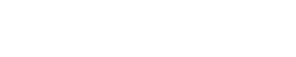 |
この近くに野崎さんの菩提寺があった
|
芭蕉が生まれた生家は通りに面し、表は格子構えの古い町家で、玄関から奥まで通り土間となっている。芭蕉は正保元年(1644)松尾与左衛門の次男としてここで生まれた。芭蕉の伝記の中で最も古く信頼される『蕉翁全伝』(宝暦12年(1762)川口竹人稿)に「正保元甲申の年、此国上野の城東赤坂の街に生る…」とある。出生月日は不詳。
幼名を金作、長じて宗房と名乗り、通称は甚七郎、忠右衛門と称したとも伝わる。2男4女の3番目で、兄半左衛門のほかに姉一人妹三人がいた。10代の後半、上野の町で盛んであった俳諧に興味を持ち、先輩俳人たちに手ほどきを受ける。そして19歳の頃、藤堂藩の侍大将藤堂新七郎家に奉公に出る。仕えた身分は台所用人とも料理人とも
伝えられている。跡継ぎの良忠は蝉吟と号し、京都の北村季吟に俳諧を学んでいたことから、俳諧好きであった芭蕉も良忠と共に俳諧に励んだといわれる。ところが、良忠は25歳の若さでこの世を去ってしまい、芭蕉はまもなく藤堂新七郎家を退身した。時に23歳。その後数年間のことはあまり知られていないが、伊賀上野に住まいをしながら俳諧
の修業のため、時折京都にも 出かけ古典や俳諧に必要な学問を修めたといわれる。その研鑽の結果が、寛文12年(1672)29歳の1月、伊賀の俳諧仲間を集め初めて編んだ三十番発句合の『貝おほひ』である。この『貝おほひ』を文学の神で連歌の神でもある上野天神宮へ奉納、俳諧師として世に立つ決意を示し江戸へと旅立って行った。
江戸へ出てからもふるさと伊賀上野へは旅の途中度々帰郷している。芭蕉にとって青年時代までを過ごしたこの生家はふるさとを実感できる安らぎの場所だった。生家の裏庭には釣月軒と呼ばれる建物が建っている。ここは芭蕉の青年時代の書斎で『貝おほひ』を執筆した記念すべき文学遺跡である。文机と行灯が置かれた質素な部屋に
若き日の芭蕉の姿が300年を越え蘇ってくる。また、通りに面して芭蕉が「笈の小文」の旅で帰郷したとき詠んだ「古里や臍のをに泣としのくれ」の句碑が、昭和38年(1963)翁の270回忌を記念して建てられている。
|
75回 04/7/24(土) 神戸地下鉄三宮駅→(電車)名谷駅→(市バス)布施畑→磨崖仏→太山寺→石戸神社→保養センター→地下鉄学園都市駅→(市バス)JR朝霧駅→大歳海岸→JR朝霧駅→(電車)JR三宮駅→神戸市役所→JR三宮駅
今回は斎藤さんの企画・案内。所用多く参加10名とやや寂しい。三宮9時出発。初めてと云う方の多い神戸地下鉄で名谷駅へ約20分。駅前の開発の立派さに驚嘆するもの多し。バスは出たあと、1時間1本のバスを待つことに。このあたりは田舎並か。昼飯の近くでの、ビール入手可否に両論。安全をみて1kgの氷と共に買って行くことにする。
バス10時13分発。10分余りで降り、磨崖仏観賞へ。市内とは思えない静けさである。太山寺は予期せぬ大きさ。奥の院で弁当をひろげる。心配したビールもよく冷えており問題なし。暑さのためか、はたまた酒豪欠席のためか、酒は半分持ち帰り。ブランデーは封を切らず。あと立ち寄り先の保養センターでは温泉もあり、結構な賑わい。
普段余り口にしない、かき氷やクリームぜんざいなどを食す。あと中内さんの「流通大学」のある学園都市駅からバス約20分でJR朝霧駅へ。昨年、花火大会の連絡橋での事故犠牲者の慰霊碑に頭を垂れる。海岸に出て「堀江ビヤ樽ヨット」の実物を観賞したところで時刻は午後3時前。折りしも今夏最高の気温。炎天下の海岸散策は断念し、
予定の大歳山遺跡古墳などはのちの楽しみに残しておくこととする。さて、残り時間の活用は?。JR三宮へ取って返して、神戸市役所最上階の展望台へ。しばし震災後の復興のさまに眼を見張る。建設中の神戸空港は霞の彼方。地下街での夜の部は早めの4時過ぎから。寡ってのビヤホールはメニューと共に和風への模様替え。歳月の流れを感
じる。暑さのため一部予定を残すことになったが、スローライフもまた楽しからずやである。斎藤さん、感謝と共にまたの企画を待っています(約10千歩)
「新興の街に大きな百日紅」
・一面トップ:大阪市三セク 元部長らの告訴検討 野菜産地偽装問題「食の安全」重視(毎日)
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |