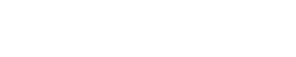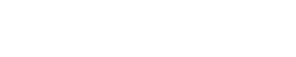古池や・・・の句碑
伊賀上野には「芭蕉五庵」(無名庵・蓑虫庵・東麓庵・西麓庵・瓢竹庵)と呼ばれる芭蕉にゆかりの草庵があった。その中で唯一現存するのがこの蓑虫庵。芭蕉の門弟服部土芳は、貞享5年(1688)3月4日ここに庵を開き、些中庵と名づけた。当時城下町の最南端に位置し閑静な場所であった。折りから「笈の小文」の旅で伊賀上野 に帰郷していた
芭蕉が1週間後の11日にこの庵を訪れ、庵開きの祝いに「みのむしの音を聞にこよ草の庵」の句を贈ったことから、上五の「みのむし」を取って蓑虫庵と呼ばれるようになった。庵は元禄12年(1699)12月に焼失しましたが、土芳の俳友たちの援助により再興された。土芳はここを伊賀における俳諧道場として、芭蕉没後も蕉風俳諧を普及させるため
尽力した。庵はその後も荒廃したり所有者の変遷を経たが、昭和30年(1955)12月に上野市の所有となり、翌年から一般公開している。庭内には、芭蕉堂や芭蕉の代表句「古池や蛙飛こむ水の音」をはじめとする句碑が建ち並んでいる。絶え間なく小鳥のさえずる声や、四季折々の花が咲きそろう閑寂な庭内に一歩足を踏み入れると市井の喧騒
から抜け出し、わび・さびの世界を感じることができる。「音の一句」なる投句箱があったが、誰も見向きもせず。
|