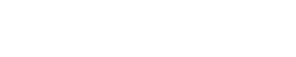 |
|
|
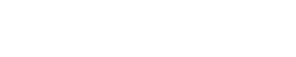 |
一里塚とは、1里(約4km)ごとに街道の両脇に塚を築き、榎を植えて、街道の路程の目印としたもの。市域では梶原と芥川にありましたが、現在は旧芥川宿東口の東側だけに残り、平成5年3月に府の史跡に指定されました。
|
西国街道の芥川一里塚から芥川橋までの間、約400mの町並み。かつて旅籠屋などが立ち並び、大名行列や旅人らが行き交う北摂の要地でした。現在は変貌が進み、宿場の面影は失われたものの、わずかに残る格子窓の二階家に往時がしのばれます。
|
全長350m・全幅340mの広大な墓域を誇る、淀川北岸最大の前方後円墳。今城塚の名は戦国時代に砦として利用されたことによるといわれています。
墳丘の形状や出土埴輪などから、真の継体天皇陵(現継体陵の太田茶臼山古墳は、築造時期からみて継体天皇の没年(531)と一致しない)と考えられています。昭和33年2月に国の史跡に指定されました。
|
74回 04/6/26(土) 近鉄上野市駅→だんじり会館→伊賀流忍者博物館→俳聖殿→上野城→とろろ庵伊賀路→鍵屋の辻→伊賀越資料館→本町通り→中之立町通り→蓑虫庵→寺町通り→芭蕉翁生家→近鉄上野市駅
菊池さんのこの会への参加も、昨年8月の金沢が最後になってしまった。そのうちのカムバックを期待していただけに、残念の極みである。今となってはご冥福を祈るばかりである。合掌。
さて、梅雨の最中、雨中の散策を覚悟で当地を計画するも、幸いにして降られず。有り難いことに、ご先祖が当地出所の野崎さんに案内をして頂くことになる。野崎さんをはじめ、皆さん早い集合。こんなことなら一列車早くすればよかった。車中歓談のうちに、1時間51分もあっと言う間に上野市駅に着く。駅前には芭蕉の像が、今年は生誕360年
とかで、キャンペーンの幟が道中いたる所に立っていた。先ずは、だんじり会館へ。岸和田と違ってだんじりは硝子越しの観賞で周囲をめぐる形になっている。大画面では、祭り・だんじりの他にも、城など上野市の四季を紹介。次の忍者博物館では、どんでん返しなど色々の仕掛けを実演で披露。忍者使用の道具類も展示されていた。上野公園内の
俳聖殿を経て上野城へ。この辺りで早くも昼時。往復約1時間をかけて、珍しい「麦とろ」を食しに。麦飯とは云え、麦は4割。それも黒い筋は取られており、且つ米粒大に砕いてあるため、見た目には麦飯とは思えない。が、口に入れると懐かしい食感。とろろのだしがまた美味く、絶妙な喉越し。なぜか石焼きの「タン塩」との取り合わせが最高。
早速、夜の部で「タン塩」を所望する人も。食後は野崎邸を経て「甚七郎(芭蕉幼名)散歩道」を歩む。最終の芭蕉生家で五時前。予定コースの全部は無理だと思っていたが幸い踏破できる。夜の部も駅近くの「食彩酒房」で野崎さんもご一緒に。梅雨の晴れ間、野崎さんの名ガイドで伊賀上野を堪能した一日だった。(約20千歩)
「梅雨晴れ間芭蕉の里を遊びけり」
・一面トップ:大手消費者金融子会社の幹部 個人信用情報7000件売却 1000万円不正利得(毎日)
|
旅に生き旅に人生を見いだした漂泊の詩人松尾芭蕉の銅像が近鉄上野市駅前広場に建っていまる。昭和38年(1963)10月12日、芭蕉翁270回忌に上野ロ-タリ-クラブ創立10周年記念として上野市に寄贈されたもの。像の高さは2メ-トル60センチ、台座は4メ-トル余りにも及ぶ。旅笠を背負い手に杖を携え大空を仰ぎ悠然と立つ姿は、
旅に住処を求め、新たな旅に出立しようとしているかのようだ。製作は上野市出身の彫刻家で二科会員の故大西徹山(本名金次郎)氏によるもので、氏は製作にあたり、芭蕉翁の門弟たちが書き残した肖像画や容姿・人相を参考にしたり、陶像・木像さらにブロンズ像に至るまで研究しイメ-ジづくりを行った上、造形芸術の発達した南ヨ-ロッパ
にも出かけ構想をねり製作されたというエピソ-ドが伝わっている。芭蕉翁生誕地上野市のシンボルとして親しまれている。
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |