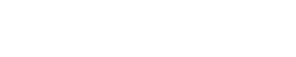 |
|
|
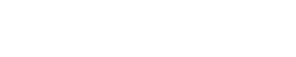 |
南北朝の時代、入江氏が居館を築いたのがはじまりとされます。永禄12年(1569)に和田惟政が城の基礎をつくり、天正元年(1573)には高山氏が町屋をも堀で囲いこんだ堅固な城を築城。特に高山右近はキリシタン大名として知られた武将で、城内に教会堂やセミナリオを建てて宣教師を保護したため一時はキリスト教布教の重要な拠点とも
なりました。元和3年(1617)幕府は、西国監視の重要拠点として高槻城の直営修築に着手。その結果、3層の天守と高石垣・土居を備えた近世城郭としての高槻城が出現。慶安2年(1649)には、永井直清が高槻城に入り、以後13代、幕末まで高槻を治めましたが、明治7年(1874)、石垣石を鉄道工事に使用するため高槻城は破却され、
城跡は昭和25年、府の史跡に指定されました。現在は一部が城跡公園として市民のいこいの場となっています。
|
しろあと歴史館では、開館1周年を記念して「発掘された埴輪群と今城塚古墳」を展示していた。今城塚古墳は、淀川流域最大の規模を誇り、継体天皇の陵墓と考えられている。
発掘調査により日本最大規模の埴輪祭祀場が確認され、家や人物・動物など多彩な埴輪が大量に発見された。これら大王陵の葬送儀礼に迫る貴重な埴輪群像を、三島古墳群出土の埴輪や復元CGも交えて展示していた。
[主な展示品]
千木を飾る高床の家/両手を高く掲げる巫女/甲冑をまとう正装の武人/楽座の人物たちなど、埴輪約70点。残念ながら、撮影禁止だったので、ご興味のある方は、つぎのホームページをご覧ください。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi/shiroato/
|
高槻城下から西国街道へ至る松並木。かつて、城下町には6箇所の出人口があり、その1つ京口から西国街道へ至る八丁(約900m)の間は、数百本の老松が立ち並び、「八丁松原」と呼ばれました。慶安2年(1649)、高槻城主永井直清によって整備されました。
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |