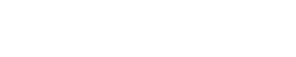 |
|
|
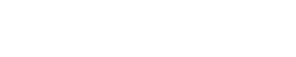 |
定林寺跡付近に珍しい白タンポポが咲いていた
|
創建や沿革については、よく解っていない。寺伝によると聖徳太子御建立四十六ヵ寺の一寺とするが、その創建や寺史については全くわからない。しかし、現在の定林寺の西側、字奥の堂の神社境内に塔跡をはじめ土壇や礎石などの建築遺構があり、昭和二十七年石田茂作氏らの発掘調査の結果、塔の心礎が確認され、
さらに朔像の菩薩の残欠や素弁蓮華文の瓦片などの出土があって、飛鳥朝創建の寺院であることが確かめられた。また昭和二十八年十二月に行われた日本考古学協会の発掘調査では、塔跡と廻廊跡の発掘調査が実施された。その結果、塔跡では地表下六尺七寸(約二メートル)の位置に東西九尺三寸(約二・八二メートル)、南北五尺八寸
の花岡岩の石材に径二尺七寸(約八二センチ)、深さ三寸(約九センチ)の円形柱座を掘り込んだ心礎が検出された。また地表面から心礎までの空洞を埋めたなかに朔像片、古瓦片などが遺存していた。また廻廊についても一部発掘が実施され、桁行八尺二寸(約二・四八メートル)、梁間九尺(約二・七メートル)の建物であったことも確認された。
|
高さ一〇六センチメートルの石棒状の立石の一種と考えられている。 その形から一種の男根石とみられ、俗に「まらいし」と呼ばれている。もともとは、垂直に立っていたものが、傾いたものと考えられる。
<由緒について>
古代の性器信仰によるものか、また坂田寺の北西の境界石等、何かの標石として使われたものか、由緒は定かではない。飛鳥川をはさんで対岸の丘陵が「ふぐり山」と呼ばれ、これと対をなすと言う話もある。
<農業祭祀との関係について>
これと関連する行事として、栢森や稲淵の網掛け祭りや飛鳥巫神社の御田植祭など、古い形態をもつ生産すなわち五穀豊穣を願う一連の豊穣儀礼とみられる。
|
ここは32回'00/12/9、「会員紀行・明日香」'02/9/25にも掲載
創建の事情や年代については明確ではないが、聖徳太子伝暦によれば太子がこの地で勝鬘経(しょうまんきょう)を講ぜられたとき、瑞祥があり、それによって仏堂を建立したとある。従来から問題視されている史料としては、河内野中寺の弥勒像の丙寅(天智天皇五年−六六六)の紀年銘に「橘寺智識之等(詣)中宮天皇大御身労坐之時、
誓願之奉弥勒御像也」とある。また法隆寺東院資材帳によると推古天皇十四年七月、「天皇詔太子日、於朕前講説勝鬘経、則依詔太子講説三日、講竟夜蓮花零、花長二三尺溢方三四丈之地、則其地誓立寺院、是今菩提寺也」とある。推古十四年という年代についてどの程度の信憑性がるかは別として、天武紀九年夏四月、
「乙卯(十一月)、橘寺尼房失火、以焚十房」とあり、また類従国史には延暦十四年四月二十日の条に「大和国稲二千束施入菩提寺以遭火災也」とある。さらに上宮太子拾遺記には久安四年(一一四八)に塔が雷火のため焼失したと伝える。これらの記事によると再三災厄をうけたらしい。平安朝になって、治安三年藤原道長が参詣し、
享徳元年の古記のある南都七大寺巡礼記には、伽羅の構成などを挙げている。中世には一部の伽羅復興が行われたらしいが、文安の頃、さらに永世三年の頃、多武峰の僧兵によって兵火に遭い、寺運は衰退した。江戸時代の様相については寛文寺社記に「いつの頃よりか衰微して、今は講堂一宇残りて、太子三十五歳の御時、みづから
作り給ふ立像の御影まします。余は、只礎の址のみ残れり」とあり、和州旧跡幽考にも「おほくの年序かさなりて、をのづから形ばかりのこり侍りけるが、頃年今春八郎太夫再興せしなり」と記し、大和名所図会には「正堂、念仏堂、僧舎一区あり」と僅かに寺の形を保っていたにすぎない。天保五年京都中井家に依頼して大修理を行なうことが企画さ
れたが、実現せず、元治元年、栢守山弥市郎、畑多根井弥太郎両氏の尽力によって再興されるにいたった。これが現在の橘寺の建物である。
|
欽明天皇陵から東へのびる丘陵の南斜面、飛鳥周遊歩道の両側にある。東に約二三〇メートルのところに天武・持統陵がある。「鬼の俎、鬼の雪隠」は、もともと古墳の石棺式石室の一組の石材(花崗岩)であり、里道上部の鬼の俎外資室の基底であり、蓋石は里道下部へ転落して鬼の雪隠となっている。扉石は失われている。
また伝説では、昔、山に鬼がいて、人や獣をとってはこの俎の上で料理して食い、下の雪隠で用を足したとかいう伝説からこの名がついたという。
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |