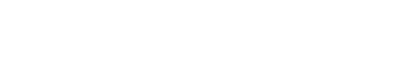 |
|
|
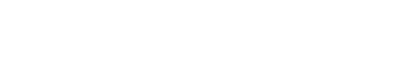 |
会員・ゲストの紀行アルバムです
|
天平の頃、行基が開いた摂播五泊の一つで、三方を山に囲まれた入江の中は波静かで室の内のようだと「室の泊」(むろのとまり)と名づけられた。帆船時代には瀬戸内海の重要な港として栄え、我国遊女発祥地として遊女に関する色々な伝説や悲話が残っている風光明媚な港町。
江戸時代には参勤交代の西国諸大名の乗船、下船地としてにぎわい、肥前屋、薩摩屋など諸藩の本陣が立ち並び、箱根に次ぐ大きな宿場として「室津千軒」とも呼ばれた。
|
海岸沿いにはコンクリートの堤防が巡らされ、道路や門の前には「防潮扉」が設置されていた。
・ 石灰の跡まだ白し台風禍 如水
|
江戸時代、室津は海の宿駅として繁栄していた。室津海駅館は、当時の商品販売と運送業をかねた買積廻船問屋で、屋号を嶋屋といい、魚屋(現在の室津民俗館)と並び称された豪商の遺構。嶋屋(三木)半四郎が江戸時代後期に建てたもので、平成6年3月に御津町の指定文化財になった。当館は、御津町が失われていく文化財を残し、
活かしていくことを目的としてよみがえらせた建物で、「室津海駅館」として平成9年4月にオープン、建物自体も重要な展示資料となっている。また、当館では、朝鮮通信使をもてなした料理(3,000円)や、大名が本陣で食べた料理(1,500円)を賞味できる。(要予約 2名様以上で3日前までに)※料理は10月末〜5月の期間のみ
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |