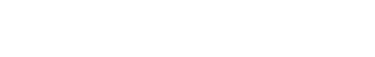 |
|
|
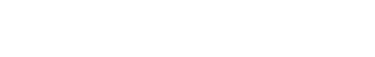 |
干菓子をお茶請けにお薄を頂く 大広間からは大刈込みの庭が見事
しばし昼寝をしていたい
1回 97/07/05(土) 近鉄郡山ーバスー慈光院ー松尾寺ー矢田寺ーバスー近鉄郡山ー
郡山城跡ー近鉄郡山
退職後も現役歩こう会に参加するも奇数月のため、偶数月開催のOB会を4人で発足。さて、なぜか集合30分前に揃う。先ず、BSすぐの慈光院、寛文3年(1663)河内小泉藩主・石州流茶道流主の片桐石州が晩年父貞隆菩提に建立。石州は普請奉行も務め自らの設計。4代将軍家綱の茶道師範。間隔の広い柱のみの大広間から眺める枯山水・
借景庭園は侘びの世界そのもの。先客退散のあとわれら4人のみ。しばし寛ぐ。ここをあとに松尾寺へ向かう。この道、街中の坂道、炎天下をあえぎ喘ぎ足を運ぶ。楽あらば苦ありか、先ほどの気分はどこえやら。やがて松尾寺、養老2年(718)日本書紀編纂の舎人親王建立の日本最古の厄除け霊場。資料を頼りに思い出そうとするも、やっと辿り
着いたとの思い以外ここでの記憶なし。HPもっと早く手掛けておけばと思う所以である。あと矢田寺への道は稜線沿いの木立豊かな道。やがて眼下に、思いのほかアジサイの群生。この時期までけなげに咲いていてくれたかと喜ぶ。矢田寺本堂は改修中。正称:金剛山寺、アジサイ寺とも。天武2年(673)勅願により開基。地蔵信仰発端の伝説あり。
ここからバスで駅まで。まだ日は高く、郡山城跡へ、秀吉の弟秀長が城郭増築の石材補充に灯篭・石仏などを使ったと聞くが、石垣に逆さまの地蔵を目の当たりにして驚き、せめて上向きに…は、甘いか。姫路城石垣に老婆が寄進した石臼を見たが、ここの人は豊臣をどう思っているのか訊いてみたい。時間もなく早々に引き上げる。柳沢文庫・町並み・金魚など、またゆっくりと訪れたい。覚悟はしていたが、ガイドブック通りにいかないことを思い知った一日だった。
「炎天下松尾寺までは地獄道」
|
あえぎながらやっと辿り着く
|
けなげな紫陽花
|
帝釈天の祠
2回 97/10/10(祭) 神鉄緑ヶ丘ー雄岡山ー雌岡山ー愛宕山ー神鉄志染
昨朝今秋一番の冷込み、天気心配するも朝を除き快晴、絶好の体育の日。珍しい神鉄沿線へ、駅から直ぐに山麓、登山口見つからず麓迂回止む無しと思う矢先、水晶探しの少年に案内される。お礼に気持ちばかりの飴玉進呈。雄岡山(おっこさん241m)山頂に帝釈天の小さな祠。南には西神の高層ビルが一望。赤土の道を下り、雌岡山(めっこさん
249m)へ向かう。途中の釣堀に糸垂れる人も、舗装の道が地道に変わるとやがて雌岡山、山頂の神出(かんで)神社は、素戔鳴命(すさのおのみこと)と奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)の間に大国主命が生まれた子孫繁栄の地。近くに男性の裸石神社、女性の姫石神社が。運良く例祭、しばし見物。神輿担手はサラリーマン風、下の道にもテント
幾つか、小部落での伝統維持の苦労に敬服。あとアップダウンののち愛宕山(163m)、山頂に享保年間の法華塔。山を下りると稲刈りの終わった牧歌的な田園風景。兼業農家か勤めの足はと余計な心配をしながら志染(しじみ)駅まで。都会近くで田舎気分満喫の一日だった。現役三人の参加も嬉しかった。
「秋祭り瑞穂の国の原風景」
|
| ● 燦咲倶楽部 | ● 次回のご案内 | ● 散策履歴 | ● 現役散策履歴 | ● 会員紀行履歴 | ● リンク集 | ● 失敗履歴 | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |