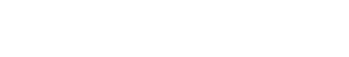 |
|
|
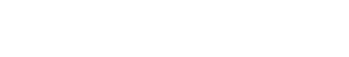 |
聖徳太子の創建と伝えられるが、はじめ観音堂だけであったという。嘉吉(かきつ)元年(1441)赤松満祐(みつすけ)が将軍足利義教(よしのり)を殺害、その逃走の途中観音堂近くに埋葬したので、将軍義勝はここに伽藍を建立し崇禅寺として菩提を弔った。
当寺には、義教の首塚、細川ガラシャの墓、崇禅寺馬場の敵討で反り討ちにあった遠城兄弟の墓がある。なお戦後復興の茶席庭園は、茶の木を植え込んた珍しいものである。
|
案内には崇禅寺門前とあり番地と地図を見比べて探したが思わぬところにあった。
大阪府は明治元年誕生したが、翌2年正月になるとその一部をさいて摂津県がおかれた。庁舎所在地には崇禅寺馬場の地が選ばれたが、庁舎建築はされず、崇禅寺伽藍のどれかを仮庁舎にしたようである。なおこの3か月後、摂津県は豊崎県と改称、さらに数か月後には兵庫県に合併されるなど、当地は行政区域の変更がくり返された。このとき、崇禅寺馬場や中島惣社にひろがる大きな森も乱伐されたという。
このあと「摂津国分尼寺伝承地」を訪れる予定であったが、何故か「柴島神社」へ向かってしまう。この間「柴島駅」で待機される永井さんのみが行かれた。
摂津国分尼寺伝承地は、天平13年(741)聖武(しょうむ)天皇が全国に国分寺・国分尼寺の建立を発願し、当寺が摂津国分尼寺にあたるといわれている。最初、広大な寺域を有し七堂伽藍・舎利塔なども構えていたが、その後長く衰退し、応永13年(1406)禅宗の寺として柴島浄水場付近に再建された。しかし浄水場拡張に伴い、当時のものと思われる礎石とともに現在地に移転した。
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |